鶴岡八幡宮
 お茶目なお奉行様でした! 


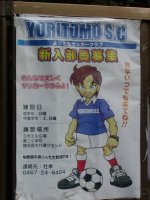 よりともS.C.! |
 お茶目なお奉行様でした! 


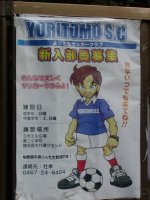 よりともS.C.! |
鎌倉市に鎮座。祭神は応神天皇、比売(ひめ)神、神功皇后。旧国幣中社。
1063年(康平6)源頼義が安倍貞任を追討する際戦勝祈願をした石清水八幡宮を由比郷に勧請したのが始まりで、その子義家は81年(永保1)修復を加えるとともに小林郷に移した。 その後1180年(治承4)平氏打倒の旗印をかかげて伊豆に蜂起した頼朝は同宮を小林郷北山の地に遷した。 都市鎌倉建設の際に、頼朝は同宮を内裏に、同宮から南に走る中心道の若宮大路を朱雀大路にそれぞれ見たてて整備した。 しかし91年(建久2)3月の大火で同宮も焼失したため、同年末には現在の位置にあたる高台を選定し、新しく石清水八幡宮を勧請して以前よりも大規模な社殿を建立した。これを本宮(上宮)、もとの社は若宮(下宮)と呼ぶ。 将軍の崇敬あつく、代々の将軍は1月1日に参詣するのが恒例であり、鎌倉幕府の政治 的守護神としての性格も併有していた。旧8月15日の放生会が大祭で、原則として東国御家人のみが参加して将軍参列のもとに流鏑馬などが催された。 祭礼等を通じて幕府内の政治的身分的序列関係を固定化する役割を果たし、幕府による御家人統制の一手段となった。
<段葛>
<源平池>
<舞殿>
<大銀杏> |